【原文カタカナ訳】 【語義考察】 【漢字読み下し】
マーカー部は原文に記されているヲシテ。
これらを誤写と見て、改修を施した上で解釈しています。
また段落の順序が入れ替わっている部分があると思われるため、それも修正しています。
<天元の八尊は>
ヤヲヨロノ オヱテコトホキ やをよろの おゑてことほき 八百万の 生えて 寿
サツケマス さつけます 授けます
ツキノミコトハ つきのみことは 次の尊は
アイフヘモ ヲスシヤカミノ あいふへも をすしやかみの アイフヘモ ヲスシ八神の
アテマモリ ネコヱサツクル あてまもり ねこゑさつくる 当て守り 根隅授くる ス
アナミカミ あなみかみ 天並神
スヱハミソフノ すゑはみそふの 末は三十二の
アテマモリ あてまもり 当て守り
ソムヨロヤチノ そむよろやちの 十六万八千の
ツキモノカ アテマモリウム つきものか あてまもりうむ 付きモノが 当て守り生む
ヨロモノノ ナカニヒトツモ よろものの なかにひとつも 万者の 中に一つも ム
マモラヌハ ナキトシルヘシ まもらぬは なきとしるへし 守らぬは 無きと知るべし ム →ホ17
コノユエニ フタカミオホス このゆえに ふたかみおほす この故に 二尊思す
ネコエミチ オノコロシマノ ねこえみち おのころしまの 音声道 オノコロ州の
ナカハシラ メクルヲカミノ なかはしら めくるをかみの 中柱 回る男尊の →ホ3
クチヒルオ ヒラクアネヨリ くちひるお ひらくあねより 唇を 開く 'ア' 音より
ノヘツツク ミウタオアミテ のへつつく みうたおあみて 宣べ続く 御歌を編みて
アナニヱヤ ツヰテフタツハ あなにゑや つゐてふたつは 「あなにゑや」 継いで二つは
クチフサキ フクイキムレテ くちふさき ふくいきむれて 口塞ぎ 吹く息 蒸れて
フスムウン ウンニツヰテノ ふすむうん うんにつゐての 燻む 'ウン' ウンに次いでの ニ ウンに連ねる
ツキウタハ ウマシオトメニ つきうたは うましおとめに 継ぎ歌は 「うまし乙女に」
オトメニト ナナネニアタル おとめにと ななねにあたる 'おとめ' にと 七音に当たる 主文で打ち当る
クニイツネ トメハミツネノ くにいつね とめはみつねの 地 出づ音 留めは三音の ウ ネ 陰母音の'o'と'e'
アイヌナリ あいぬなり 「あいぬ」 なり
ココニメカミノ ここにめかみの ここに女尊の
ヤワシウタ ナサケアワセテ やわしうた なさけあわせて 和し歌 情け合せて
ワナニヤシ ウマシヲトコニ わなにやし うましをとこに 「わなにやし うまし男に
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー [この部分は本来文頭にあったと思われるため、文頭に移動済み]
ヤヲヨロノ オヱテコトホキ やをよろの おゑてことほき 八百万の 生えて 寿
サツケマス さつけます 授けます
ツキノミコトハ つきのみことは 次の尊は
アイフヘモ ヲスシヤカミノ あいふへも をすしやかみの アイフヘモ ヲスシ八神の
アテマモリ ネコヱサスクル あてまもり ねこゑさすくる 当て守り 根隅 授くる
アナミカミ あなみかみ 天並神
スヱハミソフノ すゑはみそふの 末は三十二の
ヒコカミノ ミメミカタチオ ひこかみの みめみかたちお ヒコ神の 見目・見形を
アテマモリ あてまもり 当て守り
ソムヨロヤチノ そむよろやちの 十六万八千の
ツキモノカ アテマモリウム つきものか あてまもりうむ 付きモノが 当て守り 生む
ヨロモノノ ナカニヒトムモ よろものの なかにひとつも 万者の 中に一つも
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アヒキトハ マケテヤワシノ あひきとは まけてやわしの あひき」 とは 負けて和しの (我退き)
ミヤヒナリ アイヌアヒキノ みやひなり あいぬあひきの みやびなり "あいぬ" "あひき" の
ナカレキハ ケリナオヨクキ なかれきは けりなおよくき 流れ際 'けり' なお良くき "あいぬ・あひき" は "あひけり" でもOKという
コトナラス ことならす ことならず ことにはならない
イカタトカモノ いかたとかもの イカダとカモの =カイ(櫂)
ハシメヨリ ヤマトコトハノ はしめより やまとことはの 初めより 和言葉の 始まりより 音を合わす言葉
ミチアキテ タツナカツホノ みちあきて たつなかつほの 道 開きて 立つ中壺の 主要の中7音との
チマタヨリ テニオハヰツキ ちまたより てにおはゐつき ちまたより テニオハ傅き ト 分かれ目から 助詞が世話して
ミチヒキテ コトハツカヒモ みちひきて ことはつかひも 導きて 言葉遣いも 導いての
コノウタノ ナカノナナネオ このうたの なかのななねお この歌の 中の七音を
モトトシテ ヒトノムツネニ もととして ひとのむつねに 基として 人の六根に
クハリシル くはりしる 配り知る 割り当てる
ウイノヰツネハ ういのゐつねは 初の五音は イ
ミトテアシ トメノミツネハ みとてあし とめのみつねは 身と手足 留めの三音は (胴+2手+2足)
アメツチト ヒトホカマネク あめつちと ひとほかまねく 天・地と 人霊が招く 陽陰(日月)と父母の霊の3つが招く →ホ14・ホ16
ミツノアナ ウスタマシマノ みつのあな うすたましまの 瑞の孔 臼玉島の 瑞の通る孔
カヨヒチヤ かよひちや 通ひ道や
ヲカミノウタノ をかみのうたの 男尊の歌の
ソイノカス アウノヒヒキノ そいのかす あうのひひきの 添いの数 ア・ウの響きの 歌に添うオシテの数
アマレルオ ツキノハシメノ あまれるお つきのはしめの 余れるを 月の初めの 余計なのは 月初めの新月が
モチニミツ メカミノウタハ もちにみつ めかみのうたは 望に満つ 女尊の歌は
モチノスヱ マケテニヤシノ もちのすゑ まけてにやしの 望の饐え 負けて和やしの 満月の欠け 譲って調和の
ココロカク ミツルカクルノ こころかく みつるかくるの 心 掛く 満つる・欠くるの
フタウタオ ヒトツレニアム ふたうたお ひとつれにあむ 二歌を 一連れに編む
ツクハウタ つくはうた 付離歌
ツクネオアハス つくねおあはす 付く音を合わす
ソノスヱハ アシツミカワノ そのすゑは あしつみかわの その粋は 安曇川の
シマツヒコ ナカレキニホス しまつひこ なかれきにほす シマツヒコ 流れ木に干す 流木に乗って乾かす
ウノハシテ キオアミツラネ うのはして きおあみつらね 鵜の羽して 木を編み連ね
イカタノリ いかたのり 筏乗り
ケリノオヨクオ けりのおよくお 鳧の泳ぐを (=鴨)
ナカメツツ ツクルフナコノ なかめつつ つくるふなこの 眺めつつ 造る船漕の (=櫂)
オキツヒコ カモトナツケシ おきつひこ かもとなつけし オキツヒコ カモと名づけし ケリを"カモ"と名づける
コトノハオ ツイテニカヤフ ことのはお ついてにかやふ 言の葉を ついでに通ふ ついでに"カイ"に通わす
ソノカタチ アムトヤワシト そのかたち あむとやわしと その形 アムとヤワシと
ナカレキノ フツクニチナム なかれきの ふつくにちなむ 流れ木の 悉くに因む
モトツネノ アムトヤワシノ もとつねの あむとやわしの 基つ音の アムとヤワシの アノ アムとヤワシの
ツクハネオ ムスヒマシマス つくはねお むすひまします 付離根を 結びまします 陽陰の源を 生み現されます
アメミヲヤ イマフタカミモ あめみをや いまふたかみも 陽陰上祖 いま二尊も オ
ナソラヱテ ツクハノカミト なそらゑて つくはのかみと なぞらえて "付離の神" と
タタヱタマヒキ たたゑたまひき 称え給ひき
ソノトキニ ニシニサムラフ そのときに にしにさむらふ その時に 西に侍ふ (=右)
ヒルコミヤ ミコトヱヒスノ ひるこみや みことゑひすの ヒルコ宮 皇子とヱビスの ニ <と> (オシホミミとクシヒコ)
ツツシミテ ネコエノウイノ つつしみて ねこえのういの 謹みて 音声の初の コ
ミヲシヱオ キカマホシケノ みをしゑお きかまほしけの 御教えを 聞かま欲しげの 聞くことを欲す如きの
コヒネカヒ トキニアマテル こひねかひ ときにあまてる 乞ひ願ひ 時に和照る
ミコトノリ みことのり 御言宣
ウイノメクリハ ういのめくりは 初の巡りは ネ (順番)
アノオシテ アメツチワカツ あのおして あめつちわかつ 'ア' のオシテ天地分かつ (陽陰)
カタチナリ ヒトノウイネモ かたちなり ひとのういねも 形なり 人の初音も
アニアキテ クチフサキフク あにあきて くちふさきふく 'ア' に開きて 口塞ぎ吹く
イキムレテ ハナニカヨヒノ いきむれて はなにかよひの 息 蒸れて 鼻に通ひの
ウヌノネハ モトアカノホル うぬのねは もとあかのほる 'ウヌ' の音は 基 'ア' が上る 基つ音のアが上向く
オシテヨリ ミツニワカレテ おしてより みつにわかれて オシテより 三つに分れて
キヨキウト カロクチリント きよきうと かろくちりんと 清き 'ウ' と 軽く散り 'ン' と (清音の) (鼻に逃る)
ナカノヌト ミタモヒオウム なかのぬと みたもひおうむ 半の 'ヌ' と みたも火を生む
アネトナリ ツキウムツチオ あねとなり つきうむつちお 天音となり 継ぎ生む地を (陽音)
ムスフクサ ウアノワオウム むすふくさ うあのわおうむ 結ぶ種 'ウア' の 'ワ' を生む フ (ua=wa) (陰・地)
タマノヲモ アワトワカレテ たまのをも あわとわかれて 球の央も陽陰と分れて
ソトハアニ ナカハワトナル そとはあに なかはわとなる 外は天に 中は地となる (外周は天に) (中心は地となる)
オシテヨリ アハイトヤフレ おしてより あはいとやふれ オシテより 'ア' は 'イ' と破れ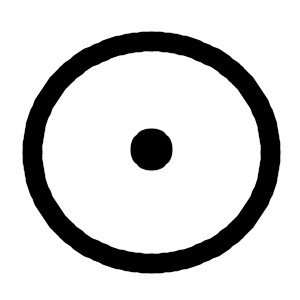
エトナカレ ワウハオトナリ えとなかれ わうはおとなり 'エ' と流れ 'ワウ' は 'オ' となり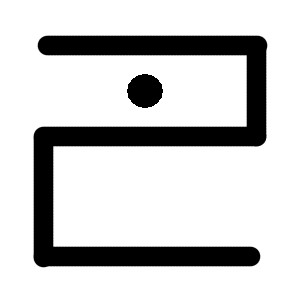
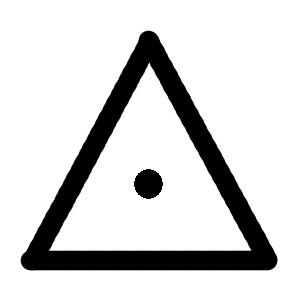
アハウツホ イハカセウハホ あはうつほ いはかせうはほ 'ア' は空 'イ' は風 'ウ' は火
エノミツト オノハニヰツネ えのみつと おのはにゐつね 'エ' の水と 'オ' の埴 五音
マシワリテ ヒトノイキスト ましわりて ひとのいきすと 交わりて 人の息すと 人が息をすることと
ナリテヨリ ヰツナナワケテ なりてより ゐつななわけて なりてより 五・七 分けて 5音・7音に分けて
ヨソヤスチ よそやすち 四十八筋 48通り
ツヰニネコヱノ つゐにねこゑの ついに音声の
ミチアキテ ナルアワクニオ みちあきて なるあわくにお 道 開きて 平るアワ国を
ヱナトシテ ヤマトヤシマオ ゑなとして やまとやしまお 胞衣として ヤマト八州を 育成の基盤として
ウミタマフ うみたまふ 生み給ふ →ホ3
ソノトキヒルコ そのときひるこ その時ヒルコ
マタトケス ムカシフタカミ またとけす むかしふたかみ まだ解けず 「昔 二尊 テ
ウミマセシ ミヲカミヒトメ うみませし みをかみひとめ 生みませし 三男尊一女 ネ
ソノホカニ イカテカクニオ そのほかに いかてかくにお その他に 如何でか国を どうやって
ウムヤラン うむやらん 生むやらん」
アメノヤワシハ あめのやわしは 陽陰の和しは ネ オ 男女の融和は
ソレナラス ウヰノアワネハ それならす うゐのあわねは それならず 初の ア・ワ 音は それにあらず 基つア(陽)とワ(陰)の音は
ナリハヰオ オシスクルナリ なりはゐお おしすくるなり 成り生いを 押し優るなり ニ 生成を 促進するなり
シカハソノ アウワハコヱノ しかはその あうわはこゑの しかばその ア・ウ・ワ は声の さればその
ヱナナラン イヤトヨアウハ ゑなならん いやとよあうは 胞衣ならん いやとよ ア・ウ は 胞衣であろう あ〜いや、アとウの音は
ネオワケス ねおわけす 根を分けず 根は同じだった
ステニワクルル すてにわくるる すでに分くるる すっかりバラバラにされた
アワウタハ ヤツノカタチニ あわうたは やつのかたちに アワ歌は 八つの形に
ムツノリノ ツネノサトシオ むつのりの つねのさとしお 六つ乗りの 常の諭しを <48神が>
クリカヱシテヨ くりかゑしてよ くり返してよ
アカハナマ イキヒニミウク あかはなま いきひにみうく アカハナマ イキヒニミウク
フヌムエケ ヘネメオコホノ ふぬむえけ へねめおこほの フヌムエケ ヘネメオコホノ
モトロソヨ ヲテレセヱツル もとろそよ をてれせゑつる モトロソヨ ヲテレセヱツル
スユンチリ シヰタラサヤワ すゆんちり しゐたらさやわ スユンチリ シヰタラサヤワ
アワミチニ ココロツクセト あわみちに こころつくせと "アワ道に 心尽せ" と ム →ホ28
ニフノカミ アメノオシヱニ にふのかみ あめのおしゑに ニフの尊 陽陰の教えに ネ (ヒルコ) アマテルの教えに
ヤヤサメテ ヤワシワラハス ややさめて やわしわらはす やや覚めて 和し笑はす (尊敬)
アワミチノ モトノココロオ あわみちの もとのこころお アワ道の 基の心を ム
ツラツラト オモンミテレハ つらつらと おもんみてれは 連々と 惟み照れば
アメノリノ コトハノハナハ あめのりの ことはのはなは アメ宣の 言葉の端は (=アワ歌)
アカハナマ アタカクノホリ あかはなま あたかくのほり アカ・ハナ・マ 天高く昇り
アナルヒノ ワカハネルマツ あなるひの わかはねるまつ 上成る日の 別・跳ねる・全つ (太陽)
タラチヲノ イキヒニミウク たらちをの いきひにみうく タラチヲの イキヒニミウク 陽陰の陽の 活霊に実受く
ソヱウタハ ヒノテノカセノ そゑうたは ひのてのかせの 添歌は 'ヒ' の手の風の ヒの母音イの 風の加勢により
ナルイキス なるいきす 成るイキス 活き素
ココロサタメテ こころさためて 心 定めて 人心を据えた後に
フヌムエケ モトヲノコエオ ふぬむえけ もとをのこえお フ・ヌ・ム エケ 基陽の声を マ 得け ウの母音を持つ子音を
ワケシレハ クハルオタキニ わけしれは くはるおたきに 分け知れば 配るお猛に 区別して知れば 火が配る勢いに
カソエウタ かそえうた 数え歌 添える歌
ヘネメオコホノ へねめおこほの ヘネメオコホノ 隔辺を乞の
ナソラエハ ヒトノヘナミノ なそらえは ひとのへなみの なぞらえは 人の隔辺の 人には久方の
アマノハラ ムムネハキヨク あまのはら むむねはきよく 天の原 六宗は清く 天上界 根の六臓を清くして
モトロソヨ オコリアカシテ もとろそよ おこりあかして モトロソヨ 驕り明かして 戻ろうよ 驕りを改めて
カヱハニニ タカエウマルル かゑはにに たかえうまるる 還えば新に 違え生まるる 還ればまた新たに 人に生まれ代わるの
タトエウタ たとえうた 喩え歌
ヲテレセヱツル をてれせゑつる ヲテレセヱツル 皇が照らして悦る
タタコトノ ウタニミチヒキ たたことの うたにみちひき 直言の 歌に導き 言葉を直す
ウムクニノ マタクトホレハ うむくにの またくとほれは 生む国の 全く徹れば 全うされれば
スユンチリ コトホキスクニ すゆんちり ことほきすくに スユンチリ 寿ぎ 直ぐに 直ゆの散り 長生きして健やかに
ミオタモツ ヨヨナカラエノ みおたもつ よよなからえの 身を保つ よよ永らえの
ヰワヒウタ ゐわひうた 祝歌
シヰタラサヤワ しゐたらさやわ シヰタラサヤワ 魄が足らす和
メハクニノ ツキトミヤヒオ めはくにの つきとみやひお 女は地の 付きとミヤビを 女は陰の 随従と協調を
アミヤワセ ヰミチアラハス あみやわせ ゐみちあらはす 編み和せ 妹道 現す
アワノウタ ワレモウタエハ あわのうた われもうたえは アワの歌 我も歌えば (妹背神)
モロヒトノ ニオウマントテ もろひとの におうまんとて 諸人の 和を生まんとて
フタソメテ サトシオシエン ふたそめて さとしおしえん 札 染めて 諭し教えん
ニノミチモ トカネハクモル にのみちも とかねはくもる 和の道も 研がねば曇る ハ
ヒルコカミ ひるこかみ ヒルコ尊 ・・・ 欠落 ・・・
・・・ ・・・ ・・・ 欠落 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 欠落 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
トキニアマテル ときにあまてる 時に和照る
ミコトノリ ムカシフタカミ みことのり むかしふたかみ 御言宣 昔 二尊
アワウタオ ヒコトニウタヒ あわうたお ひことにうたひ アワ歌を 日毎に歌ひ
ヤヲヨロカ オコナヒヰタル やをよろか おこなひゐたる 八百万日 行ひ至る
コノスエニ ワレウケツキテ このすえに われうけつきて この末に 我 受け継ぎて
ムスフテニ アサコトウタフ むすふてに あさことうたふ 結ぶ手に 朝毎歌ふ (=タミメ)
ヰクトセカ イマタカカサス ゐくとせか いまたかかさす 幾年か いまだ欠かさず
コノオシテ このおして この押し手 (=タミメ) →ホ16文・ホ23文
タマキノツクル たまきのつくる タマキの創る (タマキネ) オシヱクサ アマカミマネク おしゑくさ あまかみまねく 教え種 天神招く ミハシラキ ニココロウツス みはしらき にこころうつす 神柱木 和心 写す 神と調和せんとする心を写す ウツワモノ ソノミカタチニ うつわもの そのみかたちに 器物 その神形に モノザネ その神体に ススメコフ フカキムネアル すすめこふ ふかきむねある 進め乞ふ 深き旨ある 奉納して祈願する ソメフタオ マカセタマワル そめふたお まかせたまわる 染札を 任せ 賜る ニフノカミ にふのかみ "和の守"
ココニヒルコハ ここにひるこは ここにヒルコは ヰモノシニ カナアヤヰサセ ゐものしに かなあやゐさせ 鋳物師に 金紋 鋳させ ニ
アマネクニ オシユルミナモ あまねくに おしゆるみなも あまねくに 教ゆる御名も ワカヒルメ ニフノヰサオシ わかひるめ にふのゐさおし ワカヒルメ 和の功 (=我引きの女) ヲヲイナルカナ ををいなるかな 大いなるかな
リンク先の説明文中
★印のついたものは他の文献・サイトからの引用。
■印のついたものは筆者の個人的な意見です。
【ホツマツタヱ解読ガイド】 【ミカサフミ解読ガイド】 【ふとまに解読ガイド】
【やまとことばのみちのく】 【にしのことばのみちのく】 【あめなるみち】
【ホツマツタエのおもしろ記事】